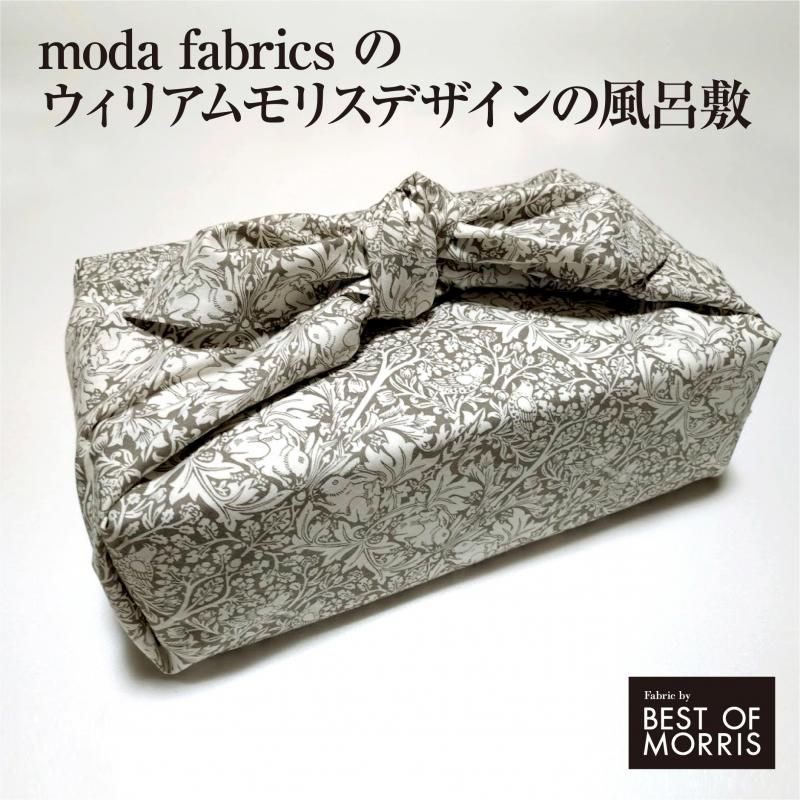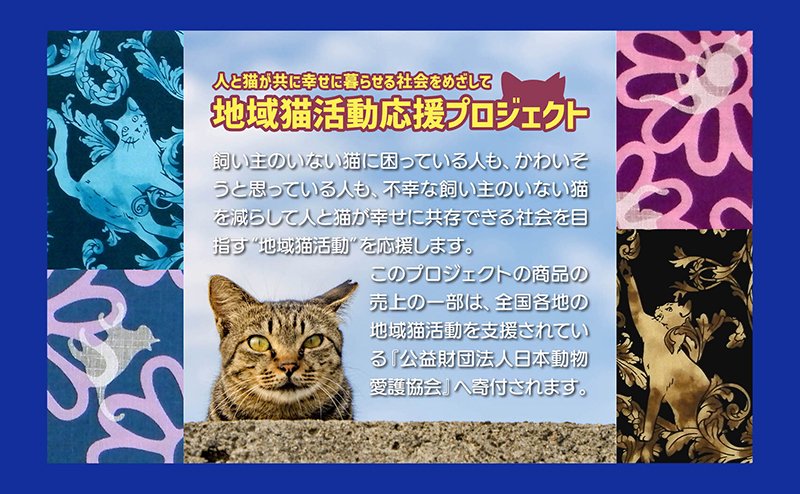ふろしきの歴史は、千数百年前にさかのぼります。長い歴史と文化を持つ一枚の布は、その時代の中で現在と異なった呼び名を与えられながら、さまざまな使われ方をし、今日のような「ふろしき」に変化したようです。

ふろしきは古くから収納に使われていた包み布
ふろしきの歴史のはじまりは奈良時代といわれています。そのころは、「平包み」などと呼ばれていた「包み布」とされ、僧侶の袈裟や楽器などを包むのに使われていたようです。また、平安時代の文献『倭妙類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』には木綿の布をはいで作られた包み布のことが「古路毛都々美(ころもつつみ)」として記されており、装束などを包んだとされています。
これらから推測すると、ふろしきは古くは「平包み」「ころもつつみ」と呼ばれていたようです。
ふろしきの歴史のはじまりは奈良時代といわれています。そのころは、「平包み」などと呼ばれていた「包み布」とされ、僧侶の袈裟や楽器などを包むのに使われていたようです。また、平安時代の文献『倭妙類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』には木綿の布をはいで作られた包み布のことが「古路毛都々美(ころもつつみ)」として記されており、装束などを包んだとされています。
これらから推測すると、ふろしきは古くは「平包み」「ころもつつみ」と呼ばれていたようです。

風呂に敷いたことに由来するふろしきの名称
包み布が現在のように「ふろしき」と呼ばれるようになったのは、風呂に敷いたことからつけられたとされています。
その説にはさまざまありますが、そのひとつに、室町時代に蒸し風呂に敷いたというエピソードがあります。
足利義満が建てた大きな湯殿に大名を招いた際、大名たちが脱いだ衣服をほかの人のものと間違えないように、家紋入りの絹の布に包んだり、湯殿に敷いて風呂から出たときに身支度をしたりするのに使われたというもので、このことから、「風呂敷」という名前になったとされています。
この説が今のところ有力とされていますが、『節用集』という室町時代の辞書は、包み布のことを「平包み」と記していることから、この時代はまだふろしきではなく、「平包み」と呼ばれていたようです。
また、このころは、一般庶民にはふろしきは普及していませんでした。
その説にはさまざまありますが、そのひとつに、室町時代に蒸し風呂に敷いたというエピソードがあります。
足利義満が建てた大きな湯殿に大名を招いた際、大名たちが脱いだ衣服をほかの人のものと間違えないように、家紋入りの絹の布に包んだり、湯殿に敷いて風呂から出たときに身支度をしたりするのに使われたというもので、このことから、「風呂敷」という名前になったとされています。
この説が今のところ有力とされていますが、『節用集』という室町時代の辞書は、包み布のことを「平包み」と記していることから、この時代はまだふろしきではなく、「平包み」と呼ばれていたようです。
また、このころは、一般庶民にはふろしきは普及していませんでした。
ふろしきが庶民に普及したのは江戸時代
では、いつごろから、ふろしきと呼ばれるようになったのでしょうか。
文献によりますと、「風呂敷」という言葉が出てくるのは、江戸時代の『駿府徳川家形見分帳』が最初とされています。
庶民にふろしきの名前が広がったのは、元禄年間に入ってからのことで、湯につかる銭湯が普及したことが、きっかけとされています。
脱いだ衣類を包んだり、ふろしきを敷いてその上で着替えたりするなどして、ふろしきが庶民に多く使われたようです。
文献によりますと、「風呂敷」という言葉が出てくるのは、江戸時代の『駿府徳川家形見分帳』が最初とされています。
庶民にふろしきの名前が広がったのは、元禄年間に入ってからのことで、湯につかる銭湯が普及したことが、きっかけとされています。
脱いだ衣類を包んだり、ふろしきを敷いてその上で着替えたりするなどして、ふろしきが庶民に多く使われたようです。
ピックアップ商品
-
6,600円(税600円)
-
6,600円(税600円)
-
6,600円(税600円)
-
6,600円(税600円)
-
3,850円(税350円)
-
12,100円(税1,100円)
-
19,965円(税1,815円)
-
30,250円(税2,750円)
-
33,000円(税3,000円)
-
3,300円(税300円)
-
4,840円(税440円)
-
4,840円(税440円)
-
2,805円(税255円)
-
2,805円(税255円)
-
3,410円(税310円)
-
3,410円(税310円)
カテゴリー
モバイル

メールマガジン
ショップオーナー

倉田千恵子
いらっしゃいませ。「ふろしきや」倉田千恵子でございます。日本の伝統と美、一枚の布の世界。ごゆっくりとご覧下さいませ。
私ども実在の店鋪は呉服屋 「染と織 くらた」でございます。趣味と実益の呉服家業は創立50年。間口を狭く奥深くのやり方で、長年、京都の染元、織元と親しくしていただき、「本物」の日本をご案内しております。軽くて、かさばらず、包む時には物に合わせて自由に形が変わる正方形の布。風呂敷で季節を包み、心を包む。四季を楽しみ、色に遊び、そして物語りと名所旧跡、絵画で包む。もう私は蒐集家になりそう。と風呂敷に惚れ込んだ私は、惚れ惚れする変幻自在の四角い布をいそいそと選ぶこととなりました。お洋服にも和服にも、男性にも女性にも、御年配にもお子様にも、お使いの良きお供としてお仕えしたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
売れ筋ランキング
-
No.11,210円(税110円)
-
No.25,500円(税500円)
-
No.35,500円(税500円)
-
No.45,500円(税500円)
-
No.52,750円(税250円)
-
No.62,750円(税250円)
-
No.74,840円(税440円)
-
No.84,840円(税440円)
-
No.96,600円(税600円)
-
No.106,600円(税600円)
-
No.116,600円(税600円)
-
No.126,600円(税600円)